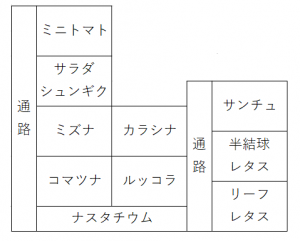啓蟄は新暦で3月6日頃から3月20日頃までです。
地中で冬ごもりをしていた生き物たちが地上へ這い出してきます。
クリスマスに咲かないクリスマスローズを観賞する
本当のクリスマスローズ(ニゲル)は12月末に開花しますが、日本では春に開花するオリエンタリスを元とした園芸品種が広く普及していてクリスマスローズと呼ばれています。
私の庭のクリスマスローズは啓蟄の頃から咲き始めます。
花に見える部分は正確にはガクです。
さまざまな色や形が楽しめます。
バケツ稲づくりセットを申し込む
3月中旬になると、JAグループが「バケツ稲づくりセット(種もみ・肥料・栽培マニュアル・お名前シール)」を配布し始めるので、ホームページから申し込みます。
JAグループ―身近な食や農を学ぶ―お米作りに挑戦(やってみよう!バケツ稲づくり)
育てた稲は秋に収穫し、ワラで正月飾りを作ります。
収穫したワラで正月飾りを作る!庭でバケツ稲づくり(2017年1月5日投稿)
活発になったメダカの点呼
啓蟄は、地中で冬ごもりをしていた生き物たちが地上に這い出してくる頃ですが、メダカの動きも突然活発になります。
冬の間は姿が見えず、全滅してしまったかと思ったメダカが姿を現します。
白いアセビの開花を確認する
我が家では、ピンクの花を咲かせるアセビと白い花を咲かせるアセビが隣り合わせに植えられています。
ピンクのアセビは雨水のころ開花し、白いアセビは少し遅れて啓蟄のころ開花します。
この時期、紅白のアセビが咲きそろいます。
ヒイラギナンテンの花の香りを嗅ぐ
啓蟄の頃、ヒイラギナンテンの黄色い花が咲きます。
つやのあるとげとげの葉の存在感が大きいため、花はあまり目立ちませんが、とてもいい香りがします。
甘いですが清涼感があり、ジャスミンやマスカットのような、フルーティでさっぱりした香りです。
水栽培のヒアシンスの花を観賞する
12月末に室内で水栽培を始めたヒアシンスが、啓蟄のころ開花します。
ラッパスイセンの花を観賞する
立春のころ咲いていたニホンズイセンは花が終了し、啓蟄の頃からラッパスイセンが咲き始めます。
モクレンの花を観賞する
この時期、モクレンが開花します。
花はぽってりと大ぶりで、花びらの外側が紅紫色、内側が淡紫色で、そのコントラストが清楚で美しいです。




















































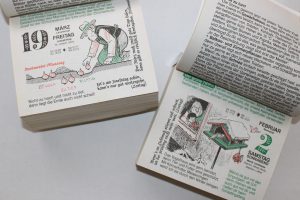

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/203b7ec5.96240180.203b7ec6.85fd7fb3/?me_id=1213310&item_id=17265655&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4005%2F9784418154005.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)