




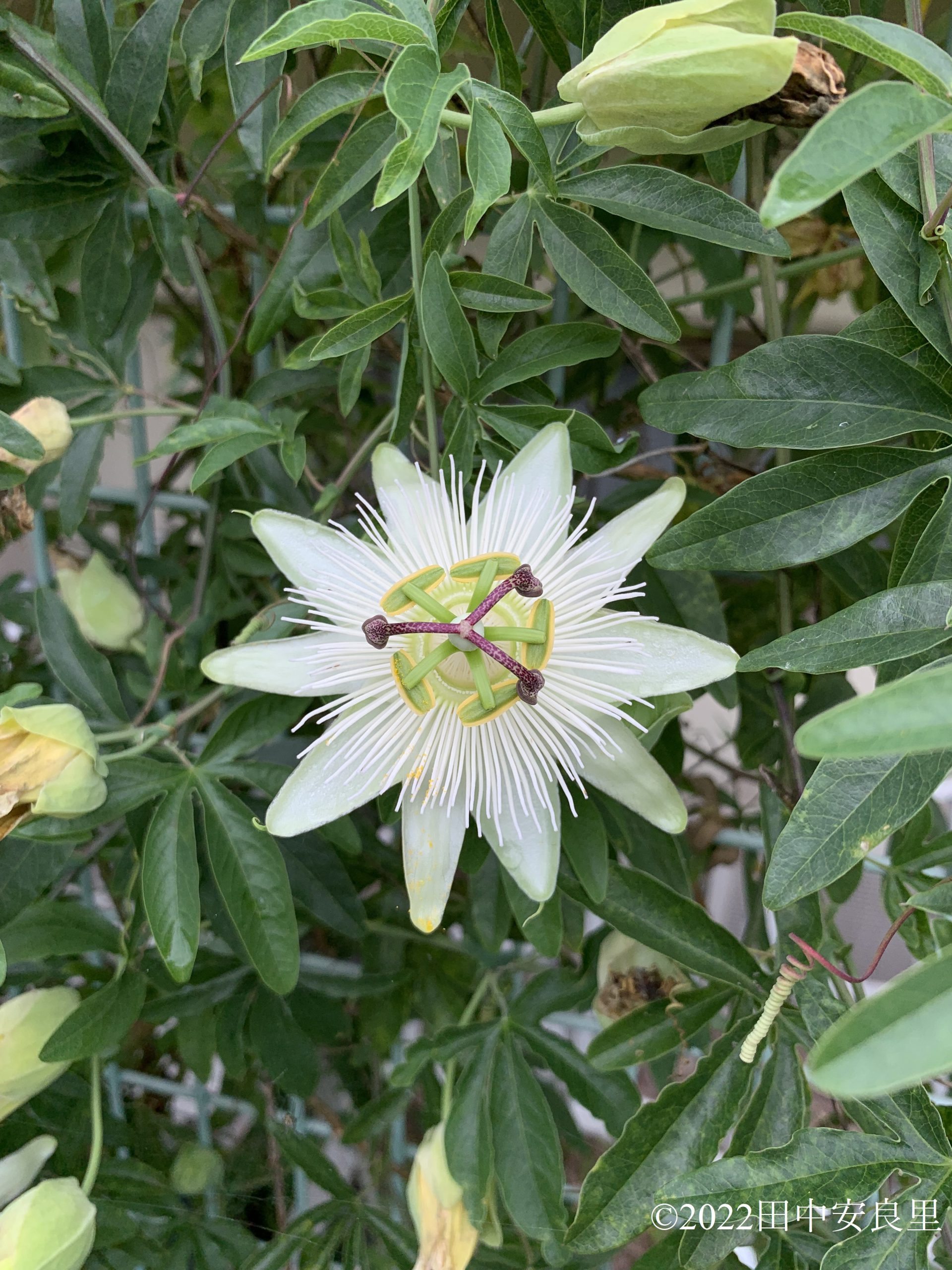
















庭を歩いていると、白くて小さいラン的な花が数十個視界に飛び込んできました。
目線と同じ高さです。
私の庭の風景としてはあり得ないものだったため、「空中にラン!?」と驚きました。
タイかシンガポールにでもいるかのような気分になりました。
我に返って一歩引いて見ると、ウメの木に着生しているランでした。
フウラン(風蘭)と思われます。
フウランは江戸時代から愛好されている園芸植物で、観賞用に購入したものを庭木につけたりするようです。
家族からは人為的にウメの木につけたという話は聞いていませんので、自然に着いて大きくなったものと思われます。
毎日歩いている場所で、葉も視界に入っていたはずなのに、花が咲くまで庭のウメの木にフウランが着生していることに気づきませんでした。
昨日までは、「家にフウランありますか?」と聞かれたら、自信をもって「ありません。」と答えていました。
自分が認識していないものは存在しないものということになっている、という、当たり前だけど非常に本質的なことを、改めて思い知らされました。
2021年下半期に生活に非常に大きな変化があり、庭の維持管理についてもいろいろと考え直す必要がでてきました。
我が家の庭は、限られた面積のわりに多様性に富んだ庭になっているので、できるだけ現状を維持したかったのですが、悩んだ末、サクラの樹を維持することは持続可能ではないいう結論に至り、切ることにしました。
大木を切るときは、精神的に非常に大きなダメージを受けます。「雑草」と言われている草は簡単な気持ちで抜くくせに、勝手なものです。
大木を切るときは、幹に御神酒をかけて、なぜ切らなければならないのかをその樹に説明します。
切った直後は、野鳥の動きが変わり、一時期、庭に設置したエサ台にヤマガラやシジュウカラが来なくなりましたが、今は元通り野鳥がやって来るようになりました。
セミがたくさんとまる樹だったため、この夏、セミの動きがどのようになるか気になります。
多くの人たちは、花が咲く時期だけサクラの樹に注目しますが、庭にサクラの樹があったおかげで、私は年間を通してサクラの樹を意識して過ごすことができました。
切ったことを納得してはいますが、各地で桜が満開になったニュースを聞くと、やはり喪失感に見舞われます。
今年も梅酒と梅シロップを作りました。
梅酒作りは私が子供のころからの年中行事です。
毎年6月になると、雑誌などで「おうちでほっこり、梅酒作り」的な特集が組まれたりしますが、私にとって梅酒作りというのはそのようなイメージではなく、もっとおどろおどろしいものです。
言語化が難しいのですが、私にとっての梅酒作りとは、梅雨、夏至、半夏生、夏越の祓といった、この時期の怖すぎるキーワードと並び、何か禍々しい雰囲気を連想させるものの一つです。
家族で庭のウメの実を収穫して梅酒を作った子供のころの懐かしい記憶と、この時期特有の怖さとが混ざり合い、この作業をしていると異次元へワープしてしまうのではないかと思ってしまう年中行事です。
こちらの木、おそらく祖母が植えたものなのですが、ずっとライラックだと聞いていました。
しかし、何か様子がおかしく、ライラックってこんな木だったのか?と思って過ごしていました。
両親に確認しても、確かにライラックと聞いているとのことで、私にとってはずっと謎の木でした。
春になって葉がつき始め、5月に花が咲き始め、改めて図鑑で調べたりネット検索をしたところ、どうやらイボタノキだということが判明しました!
Wikipediaの「イボタノキ」にこんな記述を発見しました。
「ライラックを栽培する場合に、台木として用いられる。そのため、気をつけないと、ライラックを購入して栽培しているつもりで、いつの間にか芽吹いたイボタノキの方を育ててしまい、花色がおかしいと言うことになる場合がある。」
まさにこの状態だったようです!
妹から朗報がありました。
2017年に私があげたエアープランツ(ティランジア)を大切に放置していたら、花が咲いたそうです!
エアープランツは、熱帯アメリカに広く分布し、その多くが、木の枝や岩に付着して育つ着生植物です。
風を好み、土を必要とせず、乾燥に非常に強く、葉の表面から空気中の水分を吸って育ちます。
放っておいても育つ、手のかからない植物で、土だけではなく水もいらないと誤解されがちですが、実は管理が難しく、枯らしてしまう人が続出すると言われています。
私も花を咲かせるまで育て上げたことはありません。
妹は、100均で買った小さな器に入れて、キッチンの窓辺に置き、隔週くらいで水浴びをさせ、毎日見ててやっただけと言っていました。
「毎日見ててやる」というのがポイントな気がしました。
それにしても、花は「うそでしょ!?」というくらいの紫色と黄色で、きれいすぎてこわいです。
東海地方は5月16日に梅雨入りしました。
平年より21日も早いそうです。
梅雨前にやりたい庭仕事がいろいろあり、あと2週間は庭に出られると思っていたので、あららという感じです。
この二か月間は、梅雨の晴れ間に庭仕事をして、あとはもっぱら雨量の観察です。
べス・チャトーさんに倣って!雨量計(レインゲージ)を設置する
先日、庭のサンショウの木が枯れてしまいショックを受けていたところ、別の場所で「アゲハチョウの幼虫付きサンショウの幼木」を発見し、自然ってすごいプレゼントをすると驚いたというお話をしました。
「アゲハチョウの幼虫付きサンショウの幼木」をプレゼントされました!
その後、サンショウの木を見に行ったところ、幼虫が姿を消していました。。。
旅に出るにはまだ小さいし、きっと鳥に食べられてしまったに違いない…これも「ダーウィンが来た!」的に言えば「厳しい自然の掟」だから仕方ない…と思っていたところ、
いました!
なんと、脱皮して緑色の終齢幼虫になっていました!
うまいこと周囲の緑に溶け込んでいて、
「ママ、いた!隠れてた!」という感じです!
周りに誰もいないのに、思わず田中流ジブリクイズを繰り広げてしまっていました。
正解は『天空の城ラピュタ』のルイです。
田中流ジブリクイズのやり方:日常会話にジブリのセリフを忍び込ませる!
アゲハチョウの幼虫は、鳥の糞にそっくりな色形をしていますが、脱皮をして、最終的には緑色のイモムシになります。
それにしても、自分の身を守るために敵の排泄物に自分を似せるなんて、すごすぎる戦略です。
成長すると、さすがにこんなに大きな糞はないでしょ、ということで、自分がいる環境と同じ緑色に変身するなんて、これまたすごい戦略です。
「ダーウィンが来た!」的に言えば、まさに「大自然の神秘の営み」です。
庭に樹高3メートルほどのサンショウの木があります。
サンショウは料理に使えますが、蝶好きの私にとって、アゲハチョウの幼虫の食草としても重要な木です。
そのサンショウの木ですが、2021年の春に新芽が出てこなく、枯れてしまいました。。。
大きなショックを受けていたところ、庭の別の場所に、こぼれ種から生えた高さ50センチくらいのサンショウの木を発見しました!
しかも葉の上にはアゲハチョウの幼虫が一匹乗っていました!
「アゲハチョウの幼虫付きサンショウの幼木」を絶妙なタイミングでプレゼントしてくれるなんて、自然ってすごすぎる!と驚きました。
あまりにどストライクなプレゼントに、「美女と野獣」のベルは、図書館をまるごとプレゼントされた時、きっとこんな気分だったに違いないと思いました。
柿の木のすぐ根元に生えているので植え替えたいところですが、サンショウは移植を嫌うということなので、しばらくこのまま様子を見ようと思います。